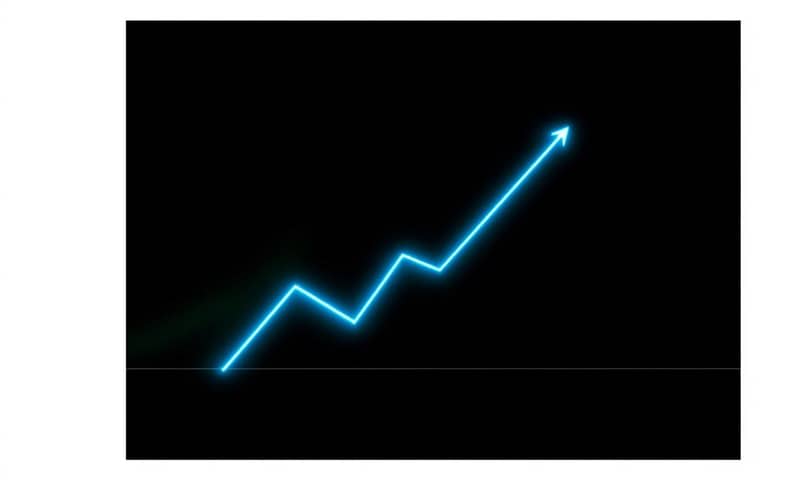最近、特にエンジニア界隈で「AIに仕事奪われる?」みたいな話、もう耳にタコができるくらい聞くよね。正直、またその話か…って思う部分もあるんだけど、でも、ちょっと見方を変えると、もっとヤバい、というか、本質的な変化が起きてることに気づいたんだ。
今日はその話を、僕なりに整理してみようと思う。これは単なる「AIツールを使いこなそう」みたいな表面的な話じゃなくて、もっと構造的な、評価制度とかキャリアパスそのものが変わっていくって話。😅
先說結論
結論から言うと、AIによってソフトウェアエンジニアの仕事が「なくなる」わけじゃない。でも、「これまでのソフトウェアエンジニア」は、もういらなくなる。これ、マジでそう思う。
どういうことかって言うと、会社がエンジニアに求める「生産性」と「責任範囲(スコープ)」の基準が、AIのせいで爆発的に跳ね上がるんだ。これについていけない人は、残念ながら「パフォーマンスが低い」ってレッテルを貼られて、居場所がなくなっていく。もうすでに、その流れは始まってるんだよね…。
CEOたちの発言に隠された「本当の狙い」
最近、GAFAとかの大手テック企業のレイオフのニュース、すごいよね。でもあれ、単なる景気後退とかパンデミック後の調整ってだけじゃないんだ。もっと深いところで、企業が「AIを使って生産性を上げろ」っていう無言の、いや、もはや隠す気もないプレッシャーをかけてきてる証拠なんだよ。
いろんなCEOがそれっぽいこと言ってるけど、特にNVIDIAのジェンスン・フアンの発言は象徴的だよね。
「AIに仕事を奪われることはない。だが、AIを使うヤツに仕事は奪われるだろう」
これ、もう答えじゃん?って思う。Microsoftのサティア・ナデラも「うちのリポジトリにあるコードの20%か30%はAIが書いてる」って言っちゃってるし、Googleのサンダー・ピチャイも「単純なバグ修正みたいな反復作業はAIに任せて、エンジニアはもっと複雑なタスクに集中できるようになる」って言ってる。
つまり、経営層から見れば「AIを使えばもっと速く、もっと多くのことができるはずだよね? なんでやらないの?」っていうのが本音。そして、それを測るための新しい物差しも用意し始めてる。

じゃあ、具体的にどう変わるの? 新しい評価軸「生産性 × スコープ」
昔からエンジニアの評価って、結局のところ「どれだけのアウトプットを出したか(生産性)」と「どれだけ広い範囲の仕事を担当できるか(スコープ)」の掛け算で決まってきたと思うんだ。
- 生産性:書いたコードの行数、修正したバグの数、書いたドキュメントの量とか、そういう具体的なアウトプット。
- スコープ:新人が小さいタスクをやるのに対して、シニアは機能全体、スタッフクラスになるとプロダクトの大きな次元を担当する、みたいな責任範囲の広さ。
で、AI時代に何が起こるかっていうと、この「生産性 × スコープ」の期待値が、各レベルで底上げされる。僕のイメージだと、こんな感じ。
これまでSWE2(ソフトウェアエンジニア レベル2)がやってた仕事の量を、これからはAIを使いこなすSWE1に求める、みたいな。そう、これまでのSWE1はもう評価されなくなる。代わりに「AI SWE1」みたいな新しい存在が標準になるんだ。
この「AI」っていうラベルは、単なる飾りじゃない。「AIを効果的に使って、従来のエンジニアよりも圧倒的な成果を出せる」っていう証明みたいなもの。マジで恐ろしい時代だよ…。
「従来のSWE」と「AI時代のSWE」は何が違うのか比較してみた
じゃあ、具体的にどう違うの?ってのを分かりやすく表にしてみた。まあ、僕の勝手な想像も入ってるけど、だいたいこんな感じになるんじゃないかな。
| 評価項目 | 従来のソフトウェアエンジニア (SWE) | AI時代のソフトウェアエンジニア (AI SWE) |
|---|---|---|
| 主な役割 | 割り当てられた機能の実装。うん、言われたことをちゃんとやる感じ。 | AIに単純作業は任せて、自分はもっと設計とか上流工程に集中する。司令塔みたいな役割だね。 |
| 求められるスキル | 特定の言語やフレームワークの深い知識。職人技みたいな。 | どのAIツールを使えば最短で課題解決できるか見極める力。プロンプトエンジニアリングも当然含む。 |
| コーディング | ゼロから自分で書くのが基本。それが当たり前だった。 | まずCopilotとかに書かせて、それをレビューして修正・改善する。自分で書くのは最終手段かも。 |
| バグ修正 | デバッガとにらめっこ。ログをひたすら目で追う…ああ、懐かしい。 | エラーログをAIに食わせて、原因の候補をリストアップさせる。人間は判断するだけ。 |
| 評価されるポイント | 「どうやって(How)」作ったか。コードの綺麗さとか、技術的な工夫。 | 「何を(What)」どれだけ速く成し遂げたか。もう結果がすべて。身も蓋もないけど。 |
| キャリアパス | SWE1 → SWE2 → Senior → Staff… 順当に階段を上っていく感じ。 | もしかしたら、AI活用実績がないと昇進できないかも?AI活用が「できて当然」のスキルになる。 |
じゃあ、僕らは今日から何をすればいい?
ここまで読んで、なんか絶望的な気分になった人もいるかもしれない。でも、まだコントロールできることはある。というか、今動かないとマジで手遅れになる。
すでに業界にいるエンジニアの場合
プライドは一回捨てた方がいい。マジで。今まで自分が培ってきた「職人技」が、AIの前では無力化される瞬間が来るかもしれないから。
- 徹底的にAIに仕事を任せる:日々の業務で「これ、AIにやらせられないかな?」って常に考える癖をつける。テストコードの生成、ドキュメントの翻訳、コミットメッセージの作成…なんでもいい。それで浮いた時間で、もっとクリエイティブな、人間にしかできない問題を考える。
- 「どうやるか」より「どう終わらせるか」:もう「この言語じゃないと書けない」とか言ってる場合じゃない。一番早く、一番楽に「仕事を終わらせる」にはどうすればいいか?そのためにAIをどう使うか?っていうマインドセットに切り替える。
- 最新のAI動向を追う:新しいLLMが出たらとりあえず触ってみる。GitHub Copilotだけじゃなくて、Cursorとか、いろんなAIコーディングツールを試してみる。そういう好奇心が、5年後の自分を救うと思う。
あ、ちなみに、アメリカのテック企業だとベテランとかTypeScriptの主要な貢献者みたいな、めちゃくちゃスキルの高い人でもレイオフされてる事例がある。これって、もう「個人のスキルが高い」だけじゃダメで、「組織全体の生産性を上げる動きに貢献してるか」が見られてるってことなんだろうな…。

これから業界を目指す学生の場合
ある意味、チャンスかもしれない。古いやり方に固執してるベテランをごぼう抜きできる可能性があるからね。
- AIでズルはしない、でもAIは使い倒す:課題をChatGPTに丸投げするのは論外。それは自分の思考力を鍛える機会を捨ててるだけ。でも、個人プロジェクトでアプリ作るときに、デザイン案を画像生成AIに作らせるとか、そういう使い方はどんどんやるべき。
- AI活用実績をポートフォリオに入れる:「このアプリ開発では、〇〇というAIツールを使って開発期間を30%短縮しました」みたいな具体的なアピールは、めちゃくちゃ刺さるはず。
- AI面接ラウンドを意識する:これから絶対、採用面接で「AIについてどう思う?」「どう使ってる?」って聞かれるようになる。その時に、自分の言葉で「AIは〇〇という課題を解決するための強力な武器だと考えていて、私はプライベートで〇〇という使い方をして成果を出しました」って言えるように準備しておくこと。
日本とアメリカでの違いは?
ここまで話してきたのは、主にアメリカのテックジャイアントの動向がベースになってる。NVIDIA CEO ジェンスン・フアンみたいな人がハッキリ言うのは、あっちの文化だよね。
日本だと、ここまであからさまに「AI使えないやつはクビだ」とはならないかもしれない。でもね、経済産業省が必死に「DXを進めろ!」って言ってるのとか、いろんな調査会社のレポートで「リスキリングが急務」って出てるのを見ると、結局目指してる方向は同じなんだよ。言い方がマイルドなだけで、水面下では同じ「生産性革命」が静かに進んでる。気づいたときには手遅れ、ってのが一番怖いパターンだよね。😅

まとめというか、今の気持ち
なんか、こうやって整理してると、ワクワクする気持ちと、正直ちょっと怖い気持ちが半々だな。変化のスピードが速すぎて、1年後にはもう全然違う世界になってるかもしれない。
でも確かなのは、この波には逆らえないってこと。サーフィンみたいに、うまく波に乗るしかない。抵抗して沈むか、乗りこなして新しい景色を見るか。僕は後者を選びたいな、って思う。
みんなは普段の仕事で、AIに何任せてる?正直、まだちょっと抵抗あったりする?もしよかったら、コメントでみんなの考えも教えてよ。🤔